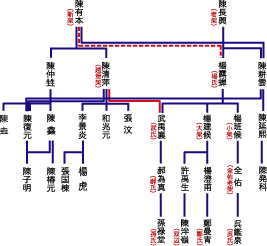|
なお、通説によれば、武禹襄はこの訣文を入手した後、永年県の自宅に戻る前に陳家溝にわざわざ出向き、師の楊露蝉が師事した陳長興に教えを乞うが、陳長興がすでに老齢のため、隣村の趙堡鎮に婿養子に行った陳清萍を訪ね、ひと月余りの教授を受けて陳氏太極拳小架式を学んだ、とされている。
武禹襄が陳清萍に陳氏太極拳を教授された時のエピソードは、今でも、趙堡鎮の村に、次のように伝えられている。
|
|
|
〜武禹襄は、趙堡鎮の陳清萍のもとに行って何度も教えを乞うが、陳清萍は
自分の太極拳は楊露蝉が学んだものとは異なるという事を理由に、教授を
拒み続けた。
しかし武禹襄は諦めず、近所に家を借りて住み着き、陳清萍一家の畑仕
事や家事を手伝い、ひたすら誠意を示し続けた。
そんなある日、陳清萍の家が火事になり、清萍が駆け付けた時には、家
はとても中には入れないような猛火に包まれており、中には妻子が取り残
されていたが、もはや為す術が無く、居合わせた誰もが燃え盛る火をただ
呆然と眺めるだけであった。
その時、武禹襄が駆けつけ、事情を聞くと身の危険を顧みることなく猛
火の中に飛び込み、自らも火傷を負いながら素早く妻子を抱えて助け出
し、村人たちは皆、その勇敢な行動を称えた。
以来、武禹襄は、その人柄を見込まれて陳清萍に教授を許され、ひと月
余りの期間に陳氏太極拳の「陳有本系新架式」の真伝を伝授された。〜
|
|
|
この時、武禹襄に伝授された陳氏太極拳は、陳有本から学んだ新架式(小架の「略」)を独自に発展させた「圏」と称される小架式であり、それは後に趙堡鎮の和兆元に伝えられ、「趙堡架式」と呼ばれて趙堡鎮を中心に栄え、発展して行った。
もっとも文革を経た今日では、王海洲氏のように「趙堡太極拳」などと、陳氏を離れた独立した太極拳を名乗り、陳氏太極拳が趙堡架式から分かれたと主張する人も居るが、それは別の問題であるのでここでは触れない。
なお、武禹襄は陳清萍に教えを受けて大いに啓発され、永年県に戻って更なる研究と工夫を重ねて「武氏太極拳」を創始している。
楊露蝉が陳家溝で三十年を費やして学んだ、陳氏の拳術を元に創造された楊氏太極拳は、中央の知識階級に歓迎されて広まり、急速に普及して、二十世紀に入るとますますの発展を見せた。
それは、日本に於いて、嘉納治五郎や船越義珍らによって、唐手や柔術などの武術が新たに理論化、体系化されて、学生や知識人の信頼を得ながら近代武道として発展していったこととたいへん類似している。
楊露蝉と武禹襄をとりまく関係を系図にすると、次の様になる。
|
|
|
|
近代の太極拳のほとんどが、楊家を中心に発展して行った経緯から、現在では太極拳と言えば、楊式太極拳のスタイルを思い浮かべる人が多いが、これまで述べてきたように、そもそも楊氏太極拳の始祖である楊露蝉が、人生の大半ともいえる時間を費やして熱心に学び、その高弟の武禹襄さえも陳家溝の門を叩き、わざわざ隣村に入り婿に行った陳清萍を訪ねてまで学び直す必要があった、根本ともいうべき武藝とは、実は「陳氏太極拳」であった。
この系図を見れば、陳氏太極拳が「現存する全ての太極拳の源流」と称される理由が理解できる。
|
 楊露蝉や武禹襄が学んだ太極拳とは? 楊露蝉や武禹襄が学んだ太極拳とは?
|
|
楊露蝉が陳家溝で太極拳を修行していた頃、族長の陳長興と同じ、第十四世伝人に陳有本と有恒という、太極拳の功夫に秀でた兄弟が居た。
彼らは、それまでの古くから存在していた太極拳である『頭套拳十三勢』の練法に工夫を凝らし、独自の新しいスタイルを創造していった。
それは、全く新しい発想による架式であったため、『新架式(小架式)』と人々に呼ばれるようになり、陳長興の架式は、それと区別して『老架式』と呼ばれるようになった。
定説によれば、陳長興から楊露蝉に伝えられた架式は、後に老架式と呼ばれた、この『頭套拳十三勢』であると言われている。
現在の楊氏太極拳の套路を見ると、表現の方法こそ違え、この「頭套拳十三勢」を基にして架式に省略、分解、代替などを加えて変革し、陳氏太極拳の「内勁」を重視して編み出されたものであるということが判る。
なお、その外形的な比較は、笠尾恭二氏の『精説 太極拳技法(東京書店1973年刊)』に詳しいので、興味のある方は是非一読することをお勧めする。
しかし、私たちは、楊露蝉が影響を受けた陳氏拳術は「老架式」だけではなく、
陳有本の「新架式」にも、非常に大きな影響を受けたに違いないと考えている。
「老架式」は、一般的には、突き、蹴り、震脚などの動作で力を込め、激しく技法を行ない、速度の快(はやい)漫(ゆっくり)も明解である。それは代表的北派拳術のスタイルであり、その外見も知らぬ人が見れば内家拳というより少林拳に近いものである。
事実、北派少林系の拳術文化圏ではつい最近まで、拳術を練る集まりを『少林会』などと称する習慣があった。少林寺にほど近い陳家溝もその例外ではなく、1920年代頃までは収穫祭で行なう武術会を同様に『少林会』と呼んでいたという。これは、陳氏も少林系拳術の影響を強く受けていたことを意味するものであろう。
「新架(小架)式」は、北派少林拳術の影響を色濃く残す「老架式」と比較すると、はるかに柔法的な要素が強く、見るからに内勁や暗勁を感じさせ、意念を用い、勁道や勁力をより意識的に練り上げようとする動きで満たされている。つまり、老架式よりもはるかに内家拳や柔拳と呼ぶに相応しいように思えるのである。
「老架式」は、陳氏太極拳が代表的北派拳術として成立して以来の、陳氏拳術の根本理論が表現されたものであった。そして、陳有本はそれを元に、より "静的" に、より "柔" を重んじて「内勁」の練功を強め、「纏絲勁」を拳理の真髄とした新しい陳氏拳術のスタイルを創造したのである。
そして、この新架(小架)式は、そのような「静・柔・内勁」等の特徴に於いて、老架式とは比べ物にならないほど、楊露蝉が創りあげた揚氏太極拳の小架式や、さらにそこから生まれた呉氏などの太極拳と共通するものが多い。
楊露蝉が「新架式(小架式の「略」)」を学んだという私たちの仮説は、それを立証する歴史的な資料も無く、それどころか『陳氏家乗』には陳長興の門徒と明記され、孫の楊澄甫も『祖父は陳長興に師事した』と明言しているので、それは個人的な直感や思い込みにすぎないと言われても仕方がない。
しかし、その "直感" にはそれなりの根拠がある。
言葉尻を捕まえるわけではないが、「陳長興に師事した」というのは、必ずしも「陳長興のみに師事した」ということにはならず、もし楊露蝉が孫にそのように伝え、周囲にもそのように語っていたのだとしたら、楊露蝉自身に「陳長興だけに学んだ」という事にしておきたかったという、何らかの "事情" があったのかも知れない。
その事情とは、その時代には絶対的であった主従関係への「義」や、下僕の身分ながら門徒として可愛がられ、手塩にかけて育てられ、その甲斐あって陳家溝で最も名を著わすまでに成長できた事への「恩義」であり、陳有本の新架に如何に魅了されても、どのような形であれ、それを学んだり研究したりすることを主人や陳長興には明からさまにできなかったのではないだろうか。
また、陳家溝といえども人間の社会集団である。もし当時、新架(小架)式が発生した事によって老架式を頑なに守ろうとする側からの反発があったとすれば、それは尚更であろう。
そして、新架(小架)式を創りあげた陳有本は、楊露蝉の師である陳長興とは同世代の人物であり、むしろ狭い陳家溝(現在でも人口は9,000人程度)の中で、当時、かなりセンセーショナルなデビューを飾った陳有本の真新しい架式に出会わない方が不自然ではないかと思う。
また、その当時の陳家溝では、陳長興の老架式を学ぶ者の中にも、陳有本の新架式に興味を持ち、老架と比較研究した者が少なからず居た筈であり、たとえ楊露蝉が陳有本に直接師事していなかったとしても、何らかの形で新架(小架)式の影響を受けていたことは、まず間違いないと思われる。
下僕として買われてきた楊露蝉少年が陳家溝に30年余りの歳月を過ごす間、初めはその才能を見出されて族長の陳長興に老架式を学び、長じた後に、陳有本の新架式に出会って、老架式とは異なるその真新しい太極拳の練法に魅せられ、その、ひたすら内勁を練る高度な拳理拳学を訓練する中で自ずと理解が湧き起り、主人の死とともに陳家溝を去ってからも更に研究を続け、老架式を基礎に新架式の演法に工夫をこらし、内勁を重視した独自の揚氏太極拳のスタイルを創始した、と考えても何ら不思議はない。
陳有本の「新架式(小架式)」の発表は、日本で言えば、茶道などの伝統藝術の家元が新しくひとつ増えるようなものであり、関係者たちにとっては、まさに大事件であったことだろう。
それは、現代日本人が考えるような、『新しく工夫した、新形式の太極拳』などという単純なものではなく、従来の「老架式」を完全に凌ぐ、高度に進化した理論と完成された練法を持つものでなくてはならなかったはずであり、それまで「老架式」に馴染んでいた陳家溝の人々にとっては、かなり衝撃的な大事件であったことは想像に難くない。
私は、一部の日本の研究家の間で、これを単に『陳有本の代から表演の架式が新しくなった』などという程度に、軽く考えられているのが不思議でならない。現代の表演用套路をいくら眺めても、練功として何が練られているか、新架(小架)式と老架式は何が異なるのかは、実際に学ばない限り、決して見えてはこない。
これは、陳家溝や近隣の村では、幾年を経ても、その新しい拳術に関する話題が絶えなかったほどの大事件であったに違いなく、隣村の趙堡鎮へ婿養子に入ったという陳清萍が、その「陳有本の新架式」を受け継ぐ人であった事から、趙堡鎮では大きな関心を呼び、またそこで門徒が盛んになったからこそ、「趙堡架式」のみならず、「忽雷架」までもそこから発生し、現代にもなお、それらが隆盛して伝えられるのだと思う。
いや、もし「入り婿説」が事実だとすれば、陳清萍が陳有本の優れた伝承者であったが故に、その血統と拳術を趙堡の地に広め増やすために、趙堡鎮から乞われて迎えられたのではないかとさえ思えるのである。
そして、楊露蝉のような、労働以外は陳一族に何の義理もない、他郷出身の下僕という立場では、自分が学んだ老架式を継続して修練する義務はなく、また、露蝉自身がすでに陳家溝で傑出した才能を認められていたことからも、師と主人の許しさえあれば、その日から堂々と新しい架式を学ぶことも可能であっただろう。
陳有本もまた、この全く新しい練法の太極拳を正しく受け継ぐことのできる、優れた人材を探し、その出現を心待ちにしていたはずである。
そして何よりも、楊露蝉のような、後に一流一派を建てるような優れた人物が、このような歴史的大事件を、自ら体験することも吸収することもなく、ただ黙って見過ごすことなど、まったく有り得ないことではないだろうか。
先に述べた武禹襄の陳家溝訪問に関しても、定説として知られるものは、
|
|
|
「武禹襄は、舞陽県塩店で兄から王宗岳の訣文を見せられ、大いに悟るとこ
ろがあり、永年県の自宅に戻る途中で陳家溝に立ち寄り、師の楊露蝉が師
事した陳長興を訪ねたが、すでに老齢のため叶わず、隣村の陳清萍のもと
にひと月余り逗留して陳氏太極拳の拳理を教授された。」
|
|
|
・・というものであるが、これでは余りにも内容が見えない。
実際には、
|
|
|
「王宗岳の訣文を見て、自身が楊露蝉より伝えられた太極拳の拳理に深く感
ずるものがあり、より高度な拳理を得る為には源流の陳家溝に行って学ぶ
しか無いと考え、先ず陳家溝に陳長興を訪ねたが、老齢ということを理由
に門前払いを食い、次に陳有本、あるいはその高弟たちを訪ねたが、これ
また厳しく断わられた。
途方に暮れていたところ、隣村に陳有本の系統を受け継ぐ、陳清萍とい
う者が居ることを聞き及び、一縷の望みを託して趙堡鎮を訪ねたが、これ
もまた門は高く、扉は厚く、 "楊露蝉の学んだものとは異なる" ことを理
由に断わられた。
しかし、これは最後のチャンスであると思い、近所に住み着いて辛抱強
く機会を待った」
|
|
|
・・・という見方が正しいのではないだろうか。
伝統武術家は、多かれ少なかれ、保守的で閉鎖的で排他的である。また、そうでなければ、真の伝承は保持できず、肝心の伝承自体が混沌とし、曖昧になってしまう。
昔日の中国武術界は、現代のように、入門料と月謝を払ってくれればドコのドナタでも大歓迎、ついでに女性は半額(!)などというコトは有り得るはずもなかったのである。
したがって、陳家溝の人間から見れば、楊露蝉の高弟だろうが何だろうが、ひょっこりとやって来た門外の武術家に、一族の至宝である拳術の真伝を授ける義務などカケラも無く、先ずは「門前払いを食らう」のが常識とみるべきである。
楊露蝉は武禹襄にとっては偉大なる師であっても、陳一族にしてみれば「その昔、薬屋の陳徳瑚が連れて来た下僕」であり、「その子がすっかり陳家溝に馴染み、成長して立派に拳術をこなす様になった」というものに過ぎず、その弟子と称する者にまで、容易に門戸を開いて教授するとは考え難い。況してや「陳有本新架」の小架式の系統はその内容に関して秘密意識が高く、文革を経た現在もなお、その真髄は極秘伝にされており、誰もがオイソレと真伝を学べるわけではない。
事実、現代の陳家溝の四傑とされる王西安氏でさえ、太極拳を学び始めた1958年当時、 (陳有本の孫弟子)に直接学んだ陳克忠の練習光景を目にして、小架式の深さと素晴らしさに感動して入門を乞うが、『王西安は陳姓に非ず(陳一族の血統ではない)』という理由で教授を拒まれ、やむなく1962年より陳照丕(陳登科の子・陳発科の弟子)に老架式を学ぶことになった、と自ら語っている。 (陳有本の孫弟子)に直接学んだ陳克忠の練習光景を目にして、小架式の深さと素晴らしさに感動して入門を乞うが、『王西安は陳姓に非ず(陳一族の血統ではない)』という理由で教授を拒まれ、やむなく1962年より陳照丕(陳登科の子・陳発科の弟子)に老架式を学ぶことになった、と自ら語っている。
武禹襄は、『王宗岳の訣文』を見て、師の楊露蝉から学んだ拳術の元となった陳氏拳術を、特に「陳有本の新架」の深遠な拳理を理解する必要性を感じた。
王宗岳の訣文には、陳氏拳術の奥義の香りが高く感じられたのである。
武禹襄は、それを確かめるために陳家溝に出向いて実際に体験し、研究しようとしたのではないだろうか。
先に述べた、趙堡鎮に伝えられる陳清萍と武禹襄のエピソードには、陳家溝に訪問しても教授を拒み続ける陳一族に対し、何としてでも教えを乞おうとして、隣村に入り婿に行った陳清萍ならば取りつくシマもあるのではないかと考え、趙堡鎮を訪問してみたが、そこはやはり婿養子ではあっても陳一族の血統、容易には真伝を教授しようとはしない。さて、どうしたものか・・・という、武禹襄の様子が読み取れる。
しかし、ある日、陳清萍宅に火事が起こり、無我夢中で妻子を猛火から救い出したことで陳清萍に心から感謝され、その行為に報いる礼としてようやく真伝を教授された・・・と、考える方が、武術家同士の関係としては自然ではないかと思う。
|